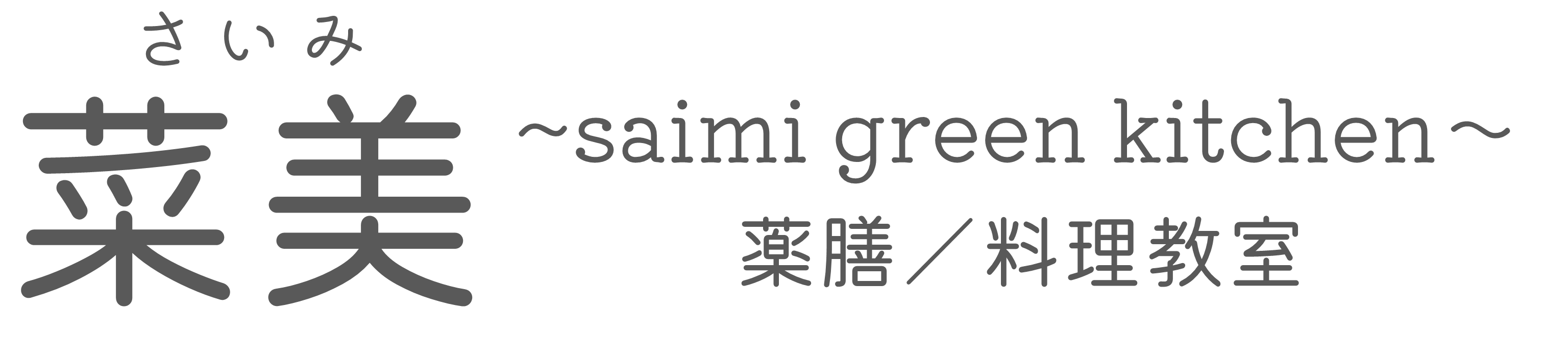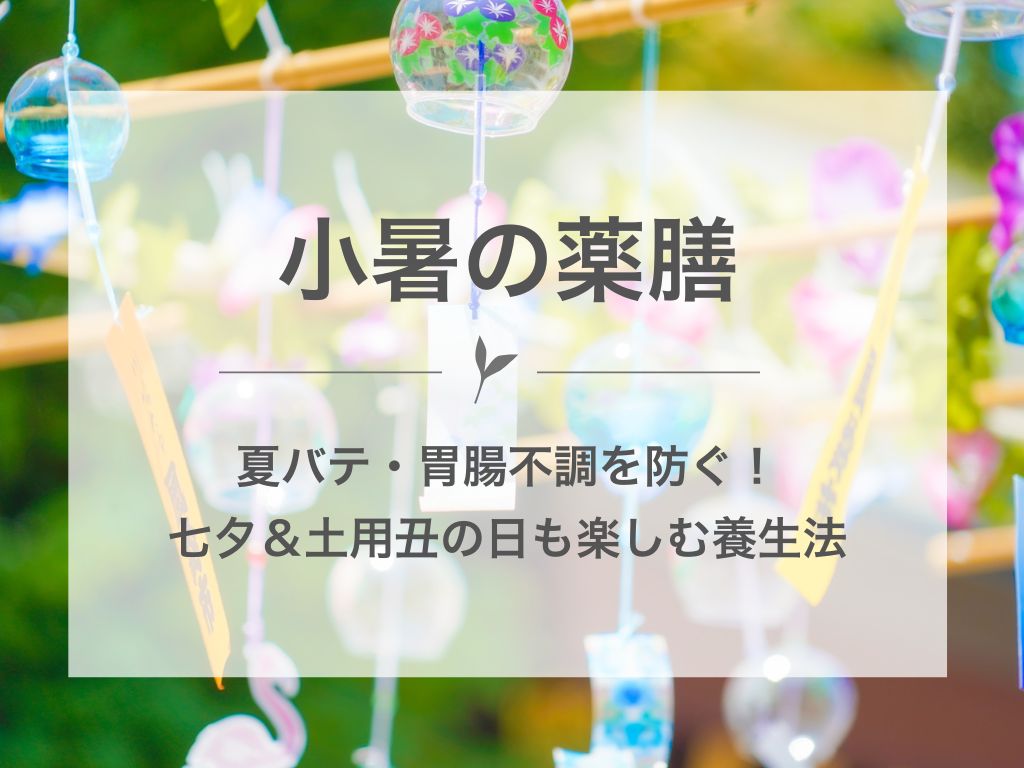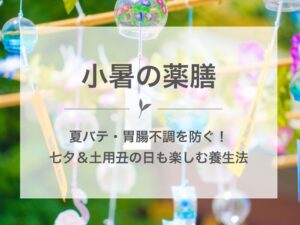2025年は、7月7日 ~ 7月21日が二十四節気の「小暑(しょうしょ)」の時期です。
いよいよ夏が本気を出し始める頃!
気温も湿度もどんどん上がり、身体にとっては試練の季節がやってきますよね。
「暑さに身体がついていかない…」
「なんだか毎日だるい…」

今回は、そんな小暑の時期を元気に乗り切るための
薬膳的養生法をたっぷりお伝えします♪
最後まで読むと、夏バテ対策のポイントやおすすめ食材がわかりますので、ぜひチェックしてくださいね♪
小暑はどんな時期?


梅雨がそろそろ明けて、本格的な夏の到来を感じる頃。
身体がやっと夏モードに切り替わるタイミングでもあります。
- 気温がグッと上がる
- 高温多湿で身体に熱がこもりやすい
- 胃腸が弱りやすい
地表が夏至から少し遅れて温まるように、私たちの身体も遅れて夏の暑さを実感するのだそうです。
だからこそ、今まで以上に 身体の熱を取り除くことが大事!
また、暑さによって 五臓の「心」 が弱りやすいので、心を養うことも忘れないでくださいね♪
小暑に起こりやすい不調と対策
小暑の頃は、まさに夏本番への助走期間。
実はこの時期に身体が疲れやすいのは理由があります。
暑さに負けないためにも、早めに対策を始めましょう!
食欲不振や消化不良


小暑は、一年で もっとも胃腸が弱りやすい時期 ともいわれます。
その影響でこんなトラブルも・・
- 高温多湿でむくみやすい
- めまいやだるさが出やすい
- 胃もたれや食欲不振が増える
こういう時こそ、消化にやさしい食事を心がけましょう。
たとえ暑くても、冷たい食事ばかりはNG!
温かい食事を基本にすることで、胃腸の負担を減らせますよ♪


また、食事の方法だけでなく、胃腸をケアする食材も上手に取り入れましょう♪
胃腸をケアする食材
なす、おくら、枝豆、しそ、さやいんげん、モロヘイヤ、味噌、はちみつ、にんじん、じゃがいも、米麹、大豆、ブロッコリーなど
熱中症になりやすい


外はうだるような暑さ。
エアコンはしっかり使うべきですが、冷えすぎには要注意です。
熱中症注意ポイント
- 室内でも水分補給を忘れずに
- 汗をかかない室内では水分の摂り過ぎに注意(消化力が下がります)
- 水だけでなく、フルーツや食事からも水分を補う
- 身体の水分を保つ食材を積極的に食べる
また食材では、暑くて汗をかいた時は熱を冷ますものや
水分を補うものを積極的に食べてケアしましょう。
身体の熱を冷ますもの
トマト、きゅうり、なす、とうもろこし、豆腐、キャベツ、スイカ
ごぼう、れんこん【生】、白菜、ほうれんそう、あさり、レタス・サニーレタスなど
水分補給するもの
トマト、きゅうり、オクラ、スイカ、にんじん、大根、豆腐、れんこん【生】、りんごなど
筋力が低下しやすい
梅雨が長引くと、運動不足になりがちに。
でも小暑の頃は、実は 体力づくりのチャンス なんです!
運動習慣のポイント
- ストレッチを毎日の習慣に
- 早朝や夕方の涼しい時間帯に軽い運動
- 室内でできる簡単な筋トレもおすすめ
無理なく体を動かすことで、夏本番の猛暑にも負けない体をつくれます♪



私は隙間時間にYoutubeでヨガ・エアロビ・ピラティスを
気分に合わせて楽しんでいます^^
炎天下での運動は避けて、涼しい時間帯を選んでくださいね♪
小暑におすすめの食材
小暑を元気に乗り切るためには、やっぱり食材のチョイスが大切!
薬膳的におすすめの食材をご紹介します♪
冬瓜


- 身体の熱を取る
- 潤いをチャージ
- 水分代謝を良くする
- デトックス
- 腫物やニキビの改善
身体の余分な熱を取りつつ、水分代謝をアップさせてくれるので、小暑の養生にぴったり。



ただし冷やす力が強いので、身体が冷えやすい人は 生姜 と一緒に煮込んだりスープにすると良いですよ♪
うなぎ


「土用の丑の日」で有名なうなぎは、この時期にぴったりのパワーフード!
- エネルギーや「気」「血」を補う
- 体力回復に効果的
- 血流改善効果



かば焼きは少々重いので、胃腸が弱りがちな人は 山椒 と一緒に食べると胃もたれ防止にもなりますよ♪
あさり


- 利尿作用でむくみ改善
- 飲酒時の酔い予防
- からだの余分な熱をクールダウン
- 血を補い、五臓「心」を養う
高温多湿でむくみやすい小暑にはぴったりの食材です♪



暑さに弱い五臓の「心」を養うのがいいですね♪^^
小暑の生活のポイント
食事や運動だけでなく、日々のちょっとした工夫で体調が大きく変わります。
お風呂上がりのポイント


夏はお風呂上がりにすぐエアコンや扇風機にあたって、汗を止めたくなりますよね。
でも、実は 汗を出し切ることが大切 なんです。
- 汗をしっかり出し切る
- 身体をきれいに拭いてからパジャマに着替える
- ベタベタ汗がさらっとするまでがポイント!
汗を出し切ることで、身体の水はけも良くなります♪
小暑の時期のイベント
小暑の頃は、日本らしい素敵なイベントが盛りだくさん!
薬膳や中医学と絡めると、さらに楽しめますよ♪
七夕


七夕の短冊に使われる 五色の色 は、中医学の五行説に基づいているのをご存じですか?
短冊の色に込められた意味
- 青(木):徳を積むこと
- 赤(火):先祖や親への感謝
- 黄(土):知人、友人への気持ち
- 白(金):決めごと、守ること
- 黒(水):知恵や知識、学業のこと
願いごとに合わせて色を選ぶと、叶いやすいかもしれませんね。



日常に中医学が潜んでいるなんて面白いですよね♪
土用の丑の日
「う」のつく食べ物を食べると良いと言われる土用の丑の日。
- うり
- うなぎ
- うどん
- 烏骨鶏 など
また、胃腸が弱りやすいこの時期は 血が不足しがち なので、精のつくものや血を補う食材を意識して摂りましょう!
鰻、肉や魚、クコの実、なつめ、ひじき、ほうれん草 など
さいごに
今回は、小暑の過ごし方について薬膳の視点でたっぷりお話しました。
小暑 のポイントをおさらいすると…
- 小暑は梅雨明けから本格的な夏への移行期
- 胃腸が弱りやすく、熱がこもりやすいので注意
- 冬瓜やうなぎ、あさりなどの食材で養生を
- 運動や生活習慣で体力維持を意識
- 七夕や土用の丑の日も薬膳と関わりが深い
これからますます暑さが厳しくなる季節。
小暑 の養生を取り入れて、元気いっぱいに夏を迎えましょうね!
ご案内
やさしく始める!おうち薬膳メルマガ(無料3大特典有り)


「薬膳って難しそう…」そんな方にぴったりのメルマガ、はじめました!
- 季節の食材&薬膳レシピBOOK
- 我が家の手作り調味料レシピBOOK
- おうちで薬膳をはじめる5STEPメール講座
が無料で届きます♪登録は1分で完了!今すぐチェック▶︎こちら
知識ゼロからの薬膳Life実践サポート講座
この講座は、初心者向けに設計した「おうちで薬膳を実践できるまで」をサポートする講座です。
私自身、薬膳を生活に取り入れるまでに多くの費用と時間がかかりました。
「薬膳をもっと身近に、もっと気軽に学べる環境があればいいのに」と強く思った経験から、当時の私が、こんな講座あったらよかったな・・と思ったものをぎゅっと詰め込みました♪


こんな方におすすめです!
- 子どもや家族の健康を守りたいけど、何から始めればいいかわからない…
- 内面から美しさと健康を手に入れたい
- 薬膳に興味はあるけど難しそう…
- 年を重ねても健康でいたい
- 大切な家族の健康を守りたい
- 決まった時間に受講するのが難しい…。
- 自分のペースで学べる方法があればいいのに…。
そんなお悩みを解決するのが、「薬膳Life実践サポート講座」 です!
詳細をご覧いただいた方全員に無料特別プレゼント(動画講座)をご用意しています♪
どんな講座なの?というのを、まずはご覧ください♪