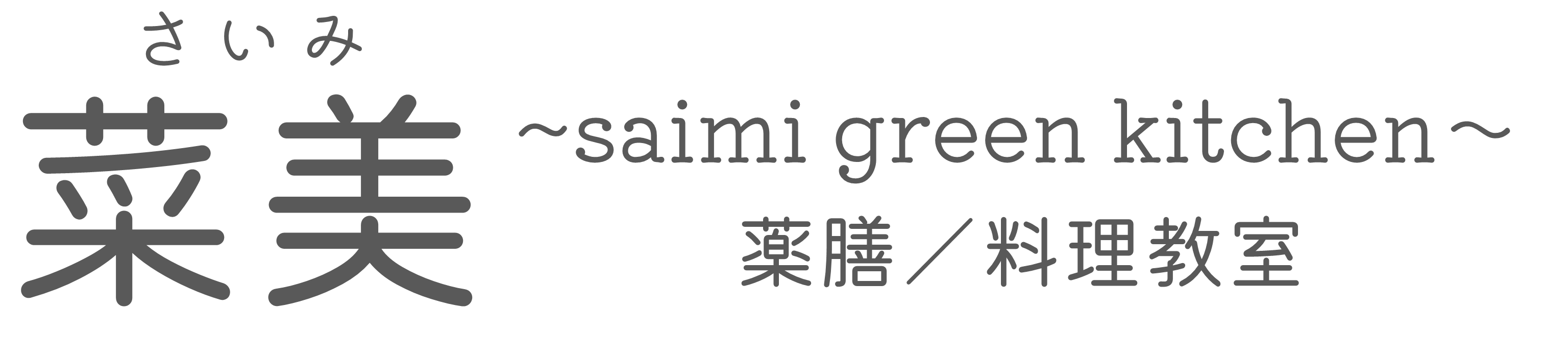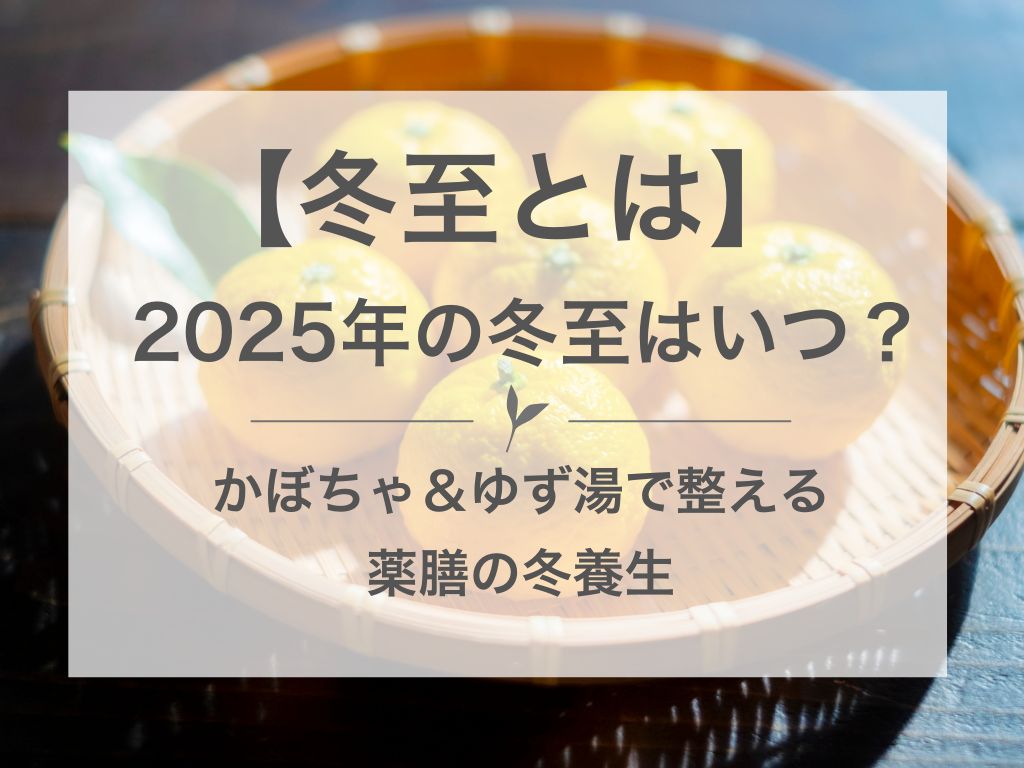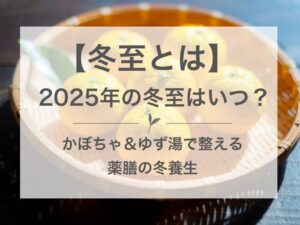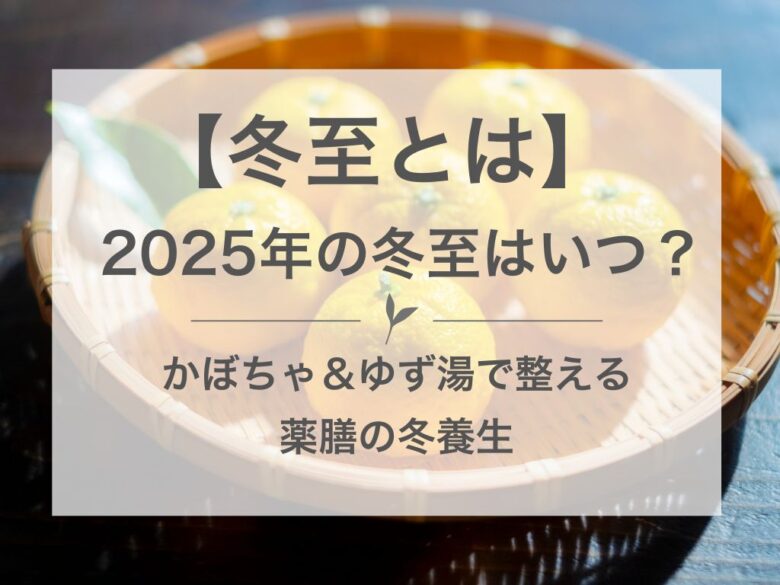
2025年は、12月22日~1月4日が二十四節気の「冬至」の時期です。
この時期は、一年で昼が最も短く、夜が最も長くなる特別な節気。
「冬至に気をつけたい不調と対策」「おすすめの食材」「冬至を楽しむ生活のポイント」について、詳しくまとめました♪

季節に寄り添う暮らしは最高の健康法です♪
日常生活に役立てていただき、寒さの中でも健やかに過ごせるヒントを見つけてくださいね!
▼二十四節気巡りカレンダー


二十四節気「冬至」はどんな時期?


冬至は、「陰気が極まる」とされて、この辞意を超えると少しずつ陽気が増え始める大切な転換期です。
一年で最も昼が短く、夜が長いため、体感的にも「冬本番」を迎えたような厳しい寒さを感じる時期です。
- 陰気が極まる時期
この時期は、体内のエネルギーが少なくなり、特に陽気が減少します。
そのため、身体が冷えやすくなり、免疫力も低下しやすい状況です。 - 年末年始の行事が続く
クリスマスや大晦日、お正月などのイベントが続き、生活リズムが乱れがち。
楽しいイベントが目白押しの一方で、疲れも溜まりやすい時期です。 - 体への負担が大きい
寒さが厳しくなるこの時期は、身体への負担が大きく冷えによる様々な不調が出やすくなります。
冬至を過ぎると陽気が少しずつ戻り始めますが、
それまでは「補陽益腎(陽気を補い、腎を守る)」を意識して過ごしましょう。
しっかりと養生をすることで、次の季節をより健康的に迎える準備が整います。
二十四節気「冬至」に起こりやすい不調と対策
ヒートショックに注意


冬の寒暖差による「ヒートショック」は、特に高齢者や高血圧、糖尿病、肥満型、睡眠不足の方に多く見られます。
たとえば、暖かい部屋から寒い脱衣所、そして熱い湯舟に入るといった温度差で、心臓や血管に大きな負担がかかります。
ヒートショックを防ぐポイント5つ
- 脱衣所を暖房で温めておく
- お風呂の温度は41度以下にする
- お湯を沸かすときはお風呂のフタを開けておく
- 入浴前に水分を摂る
何かあったときのために、家族に「お風呂に入るね」と伝えておくのも大切です!
陰気が極まるこの時期は、「陽気」のかたまりでもある五臓「心」に負担がかかります。
寒さによる動悸や胸の圧迫感、不安感も起こりやすいので、心疾患の既往歴がある方は併せて注意が必要です!
心をケアする食材
紅茶、カカオ、ひじき、棗、ジャスミン、いわし、牡蠣、帆立、アーモンドなど
体温が下がる


この時期は基礎代謝が低下し、体温が下がりやすくなります。
冷え対策のポイント
- 厚手の靴下やインナー、重ね着で、貴重な身体の熱を逃がさないようにする
- 湯たんぽや電気毛布で暖かくする
- お風呂ではシャワーだけでなく湯舟に浸かる習慣をつける
冷えは免疫力の低下や血行不良につながるので、
まずは外からの保温対策をしっかり行いましょう!
内側から身体を温めることも忘れずに。
からだを温める食材
生姜、ねぎ、にんにく、シナモン、羊肉、えび、まぐろ、かぼちゃ、玉葱、ニラなど
白髪が目立つ


腎の衰えが進むと、白髪が増えるといわれています。
特に女性は42歳、男性は48歳を目安に白髪が目立ち始めますが、
それ以前から増えている場合は老化が早く進んでいるサインです。
腎は寒さに弱く、冬に弱りやすいので白髪も増えやすい時期。
しっかりと腎を補いましょう!
腎を補う習慣
- ウォーキングやスクワットで足腰を鍛える
- 耳の血行をよくするために、耳マッサージを行う
- 冷えを防ぎ、十分な睡眠をとる
腎を補う食材
さつまいも、山芋、黒豆、にら、枝豆、ブロッコリー、モロヘイヤ、栗、くるみ、黒胡麻、うなぎ、えび、鶏肉など
二十四節気「冬至」におすすめの食材(薬膳視点)
ワカメ


ワカメは腎を補い、むくみを解消し、痰を消す効果も期待できる食材です。
薬膳では「形が似ている食材はその部分に良い」と考えられていて、
ワカメは髪に似ていることから養毛作用も期待されています♪



身体を冷やすから、温める食材と一緒に食べたりスープなどで温めて食べるのがおすすめです◎
かぼちゃ


冬至といえばかぼちゃ!
温性のかぼちゃは身体を温める力があり、胃腸の働きを助けてくれます。
消化が良く、エネルギー補給にもぴったりです♪
肺を潤す働きもあるので、空咳や風邪などにも◎



我が家は最近、カレーにかぼちゃを入れています♪
スパイスもからだを温めて巡りをよくしてくれます。
シナモン


身体を温める作用が非常に強いシナモン。
冷えを解消してくれます♪
漢方薬にもよく使われているほど優秀な食材です!



100均でパウダーが売っているので、紅茶やコーヒーにひとふりするだけでも気軽に取り入れられますよ◎
ただし、温める力が強いので高熱の時や、炎症症状(ニキビや吹き出物)、黄色い鼻水や痰の時は取りすぎ注意です
冬至の生活のポイント
身体を冷やさない


冷えは万病のもとと言われるくらい、注意するべき存在です。
特にヒートショック対策として、脱衣所やトイレを暖める工夫を忘れずに。
お風呂に入る際は、湯舟にしっかり浸かることで全身を温めましょう。
また、寒さが厳しい日には湯たんぽや電気毛布を活用し、寝るときも身体を冷やさない工夫をしましょう◎
飲み物の飲みすぎに注意
温かい飲み物でも、摂りすぎると、結果として身体の熱を奪って尿として排出されます。
適量を心がけ、飲みすぎないようにしましょう。
また、冷えたビールや冷たい飲み物は避けるのがベストですが
楽しい時間を楽しむのも養生の1つ。
楽しいイベントを楽しんでも不調にならないようにするには、
普段からの養生が大切ですね♪
新しいことに挑戦


中医学では冬は内向きの季節ともいわれ、勉強や読書に適した時期です。
この機会にセミナーや講演に参加したり、新しい趣味や習い事を始めるのも良いですね♪
▼おうち薬膳をはじめてみませんか?
>【無料】薬膳レシピBOOKなど3大プレゼントを配布中♪
二十四節気「冬至」のイベント


柚子湯
柚子の香りにはメンタルを安定させ、気の巡りを良くする作用があります。
湯舟に浮かべてリラックスしながら、心身を整えましょう♪
餃子
中国では、耳の凍傷を防ぐために生まれた養生食として親しまれています。
羊肉や唐辛子など、冷え対策の食材が使われているのが特徴です。
クリスマス、大晦日、お正月
イベントごとが多い冬至の時期は、疲れが出やすかったり胃腸にも負担がかかる時期・・。
でも、この時期はこの時期で「食べたいものを食べる!」というのが私のモットー笑
そのためには、普段の養生で胃腸を整えたり、イベント後には消化に良い食事を心がけたいですね♪
まとめ|冬至は「整えて新年を迎える」ための大切な節目
- 冬至とは、一年で最も昼が短く、陰が極まる転換期
- 寒さ・冷え・自律神経の乱れなど、不調が出やすい時期
- ヒートショックや体温低下には、入浴・室内の温度差対策が重要
- 冬は「腎」を補う養生が基本。白髪・疲れやすさはサインのひとつ
- かぼちゃは体を温め、胃腸を整え、エネルギー補給に◎
- ゆず湯は香りで気の巡りを良くし、心身の緊張をゆるめてくれる
- 薬膳では、温める食材・黒い食材・海のものを意識するのがおすすめ
- 冬至は、無理をせず「休む・温める・補う」を大切にする時期
冬至は、ただ寒さに耐える時期ではなく、
心と体を整え、次の一年を健やかに始めるための準備期間です。
かぼちゃを食べる、ゆず湯に入る、早めに休む。
そんな小さな習慣の積み重ねが、冬の不調を防ぎ、春を元気に迎える力になります♪
ぜひ今年の冬至は、この記事を参考に
あなたやご家族に合った“やさしい養生”を取り入れてみてくださいね。
ご案内
やさしく始める!おうち薬膳メルマガ(無料3大特典有り)


「薬膳って難しそう…」そんな方にぴったりのメルマガ、はじめました!
- 季節の食材&薬膳レシピBOOK
- 我が家の手作り調味料レシピBOOK
- おうちで薬膳をはじめる5STEPメール講座
が無料で届きます♪登録は1分で完了!今すぐチェック▶︎こちら
知識ゼロからの薬膳Life実践サポート講座
この講座は、初心者向けに設計した「おうちで薬膳を実践できるまで」をサポートする講座です。
私自身、薬膳を生活に取り入れるまでに多くの費用と時間がかかりました。
「薬膳をもっと身近に、もっと気軽に学べる環境があればいいのに」と強く思った経験から、当時の私が、こんな講座あったらよかったな・・と思ったものをぎゅっと詰め込みました♪


こんな方におすすめです!
- 子どもや家族の健康を守りたいけど、何から始めればいいかわからない…
- 内面から美しさと健康を手に入れたい
- 薬膳に興味はあるけど難しそう…
- 年を重ねても健康でいたい
- 大切な家族の健康を守りたい
- 決まった時間に受講するのが難しい…。
- 自分のペースで学べる方法があればいいのに…。
そんなお悩みを解決するのが、「薬膳Life実践サポート講座」 です!
詳細をご覧いただいた方全員に無料特別プレゼント(動画講座)をご用意しています♪
どんな講座なの?というのを、まずはご覧ください♪